ノイズ特性(粒状性)
粒状性
(77am93、65.89、60.89)
低コントラスト分解能(低周波領域)に影響を及ぼす
粒状性悪:低コントラスト分解能悪
・DR系のノイズ
(76pm94、72am46、61.89)
「X線量子モトル(量子ノイズ)」
:最も大きな影響で入射X線量に依存する
「光量子ノイズ(CR)」
:入射X線量に依存する
「システムノイズ」
:構造モトルや電気系ノイズ
→ 固定ノイズ
「量子化ノイズ」
・DR系のノイズへの影響因子
「サンプリングアパーチャのMTF」
「サンプリング間隔」
「画像処理のMTF」
「画像表示のMTF」
ウィナースペクトル(WS):NPS
(75am95、74am95、73am94、72am94、71am95、64.91、63.90、62.89、61.91)
面積の次元を持ち、ノイズ量を空間周波数ごとに示す
自己相関関数(濃度変動)をフーリエ変換する方法と、波形を直接フーリエ変換する方法がある
$$ウィナースペクトルWS(u,v)=\frac { ⊿x×⊿y }{ N×M } ×{ |F(u,v)| }^{ 2 }$$
F(u,v):濃度変動のフーリエ変換
⊿x⊿y:x,y方向のサンプリング間隔
N,M:横、縦のマトリクスサイズ
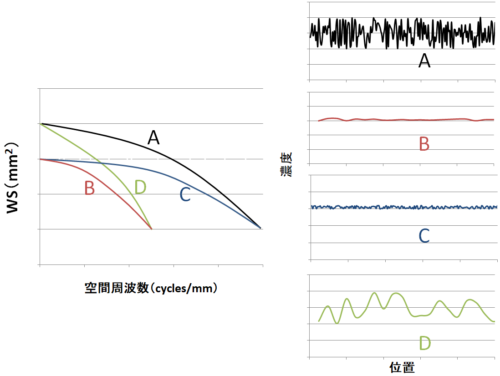
・WSが大きいとノイズ特性は悪い
・標本化間隔によって起こるエリアシングの影響を受ける
(ただし、検出器WSにはあまり影響はない)
・測定に必要なもの(61.90)
:トレンド除去処理、ピクセル寸法測定、デジタル特性曲線測定
RMS粒状度
(72pm95、61.88、60.89)
フィルム濃度のばらつきを標準偏差で表す
(RMS粒状度が大 → 粒状性が悪い)
・空間周波数ごとの情報がない
→ 濃度変動は表現可能
*変動の細かさ、濃度変動の標準偏差、周波数ごとのノイズは表現不可能
・マイクロデンシトメータのアパーチャサイズに依存する
アパーチャが広いとRMS粒状度が低下する
・アパーチャサイズ
アナログ信号を読み取る際の窓の大きさ
標本化間隔がアパーチャサイズよりも大きいと雑音特性は悪くなる
C-Dダイアグラム
(67am93、65.88、64.89、60.91)
低コントラスト分解能の視覚的評価法
バーガーファントムを使用して測定する
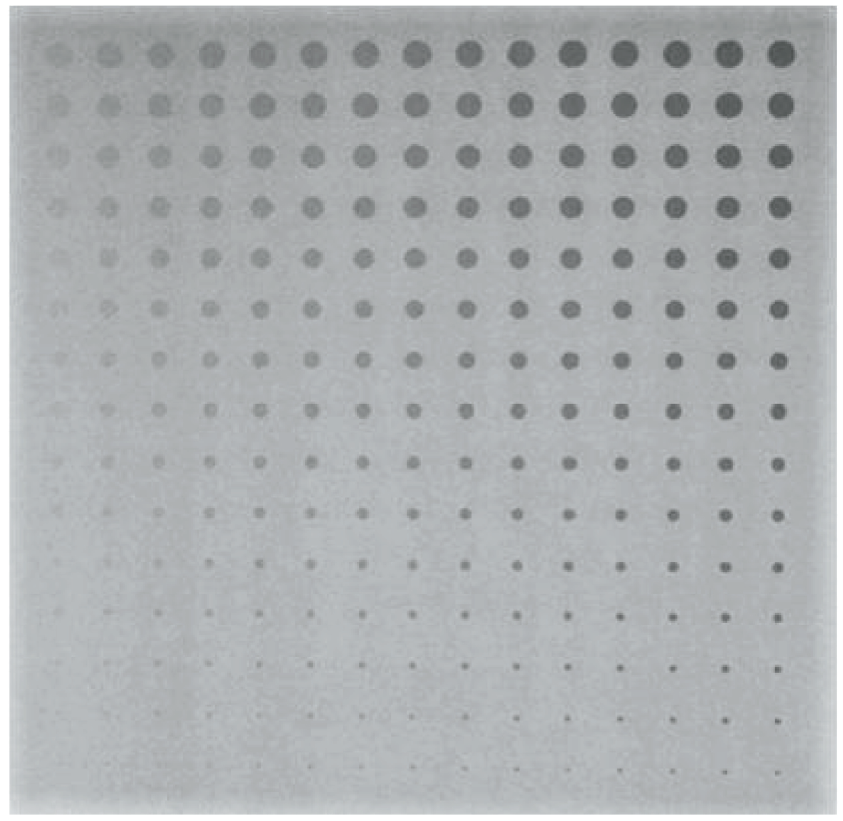
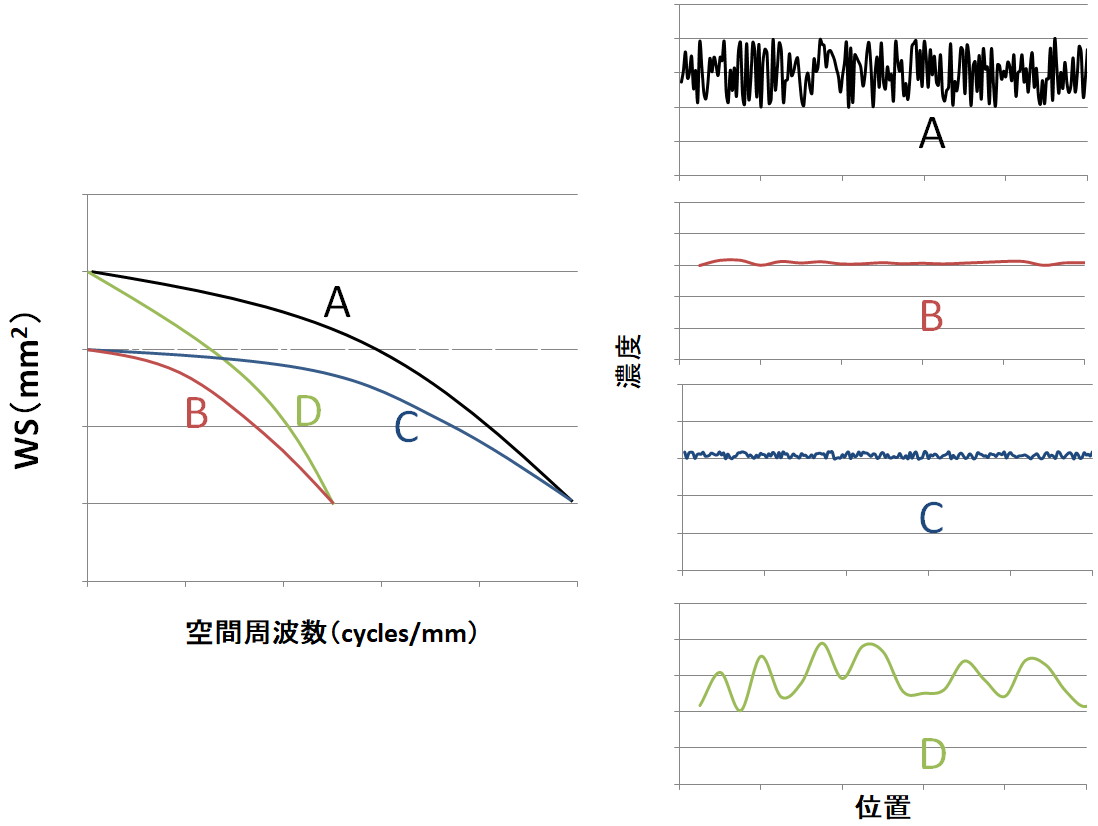
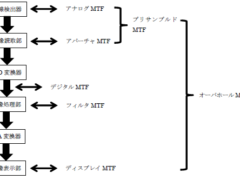
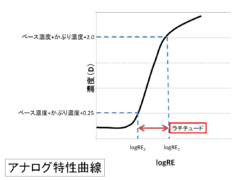
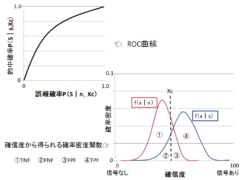





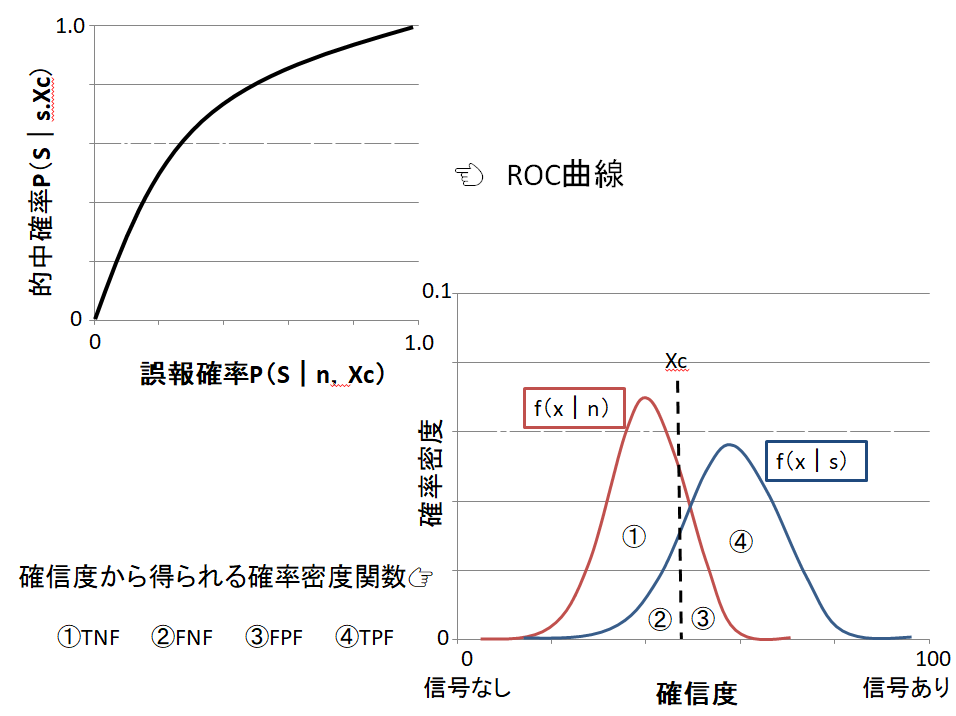
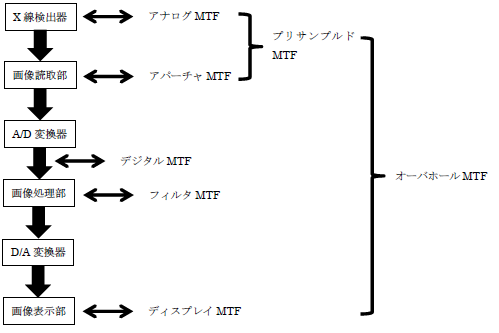
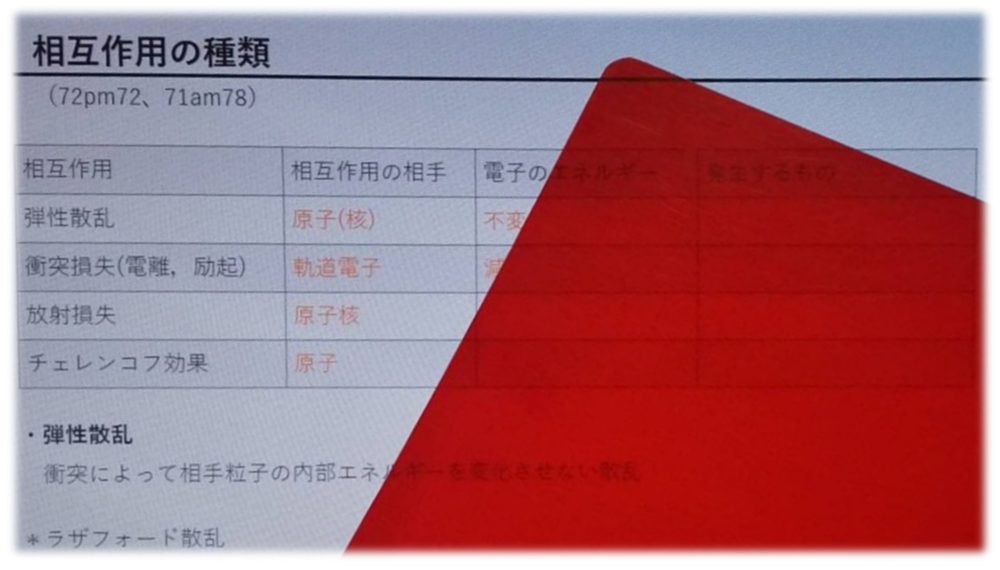

コメント